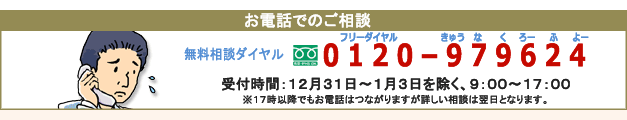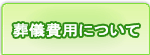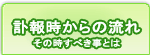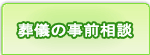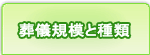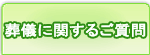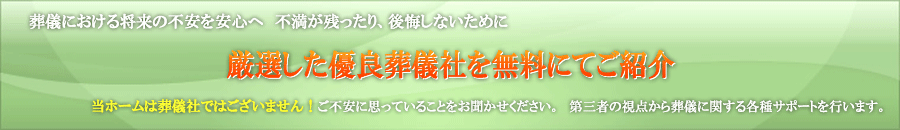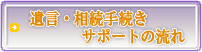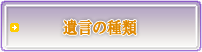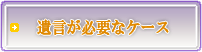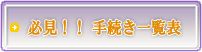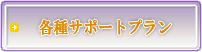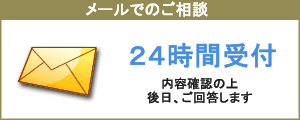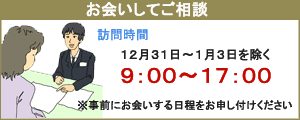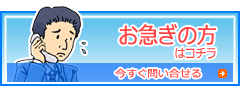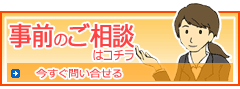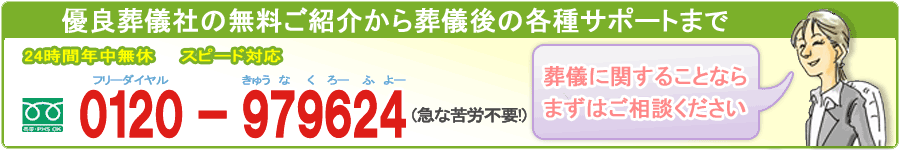逝去後にすべき手続きとは
本ページでは、ご逝去後すべき手続きをまとめてみました。 この手続きを行うことで、受取ることが出来るもの、または、 手続きを忘れてしまったために、思わぬ結果になってしまうケースもあります。
死亡後の葬儀手続
● 死亡が確認されたら死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。
(後日、各種手続きに必要になるので、原本またはコピーを複数用意しておきます)
● 市町村役場へ7日以内に死亡届を提出します。
● 提出するとその場で火葬・埋葬許可書が発行されます。
(納骨の時まで保管、納骨日に埋葬ができなくなる恐れがありますので
大切に保管してください)
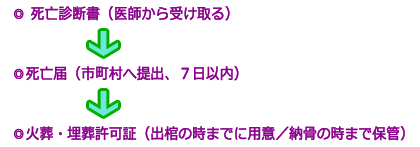
葬儀終了後の手続
● 故人の一身に専属した権利義務を解消する手続きをします。
● 健康保険証、運転免許証等の返却をします。
故人が年金受給権者だった場合、年金受給権者死亡届を提出して
年金の受給を停止します。 年金は、2ヶ月に1回まとめて支払われるため、
故人に権利があっても残ってしまう場合があります
故人と生計を同じくしていた者は、未支給年金請求書を提出して
未支給年金を受け取ることができます。 未支給年金を請求する際は、
生計を同じくしていたことを証明する必要があります。
また、状況によっては遺族年金を受け取ることができる場合があります。
なお、葬式費用は相続税法において、控除の対象になるので領収証等は、
必ず保管しておきましょう。
◎ 康保険証、運転免許証等の返却
◎ 受給権者死亡届・未支給年金請求書
◎ 祭費・埋葬料請求手続き、遺族基礎年金
銀行口座の移転手続
◎ 公正証書遺言がある場合:
公正証書遺言を提示すればすぐに銀行口座の移転ができます
◎ 自筆証書遺言がある場合:
家庭裁判所で遺言書が法的に有効かどうか検認してもらいます
● 有効だった場合、戸籍集めをします。
● 亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本を集めます。
● また、相続人全員分の現在の戸籍を集めます。
◎ 遺言書がなかった場合:
相続人同士で遺産の分割をどうするか協議をする必要があります
合意できたら、遺産分割協議書を作成します
なお、遺産分割協議書を作成する時には亡くなられた方の一生涯の戸籍、 相続人全ての戸籍を集める必要があります。 遺産分割協議書を提示すれば銀行口座の移転手続きがでるようになります。
遺族年金、遺族補償受給手続
● 遺族年金や遺族補償を忘れずにもらいましょう。
● 遺族年金や遺族補償は自ら申請をしない支給されません。
● 残された遺族の生活を保障する制度ですので、かなりの支給額になります。
◎ 遺族基礎年金
◎ 遺族厚生年金
◎ 寡婦年金
◎ 死亡一時金
◎ 遺族補償給付
子供がいる場合に支給されたり、年齢によって支給されるものがあったりなど 複雑な制度ですので、申請漏れがないように当ホームで、申請のサポートを 行っております。詳しくは当ホームまでお問い合わせください。
財産に対する税金の手続
◎ 準確定申告(個人事業をしていたり、年収が2000万円以上あった場合必要)
申請期間 : 4ヶ月以内
◎ 相続税の申告手続き
申請期間 : 10ヶ月以内
基本的に相続税がかかる場合のみ申告が必要です。
なお、相続税がかからない場合でも、配偶者の特例や小規模宅地を
利用する際には遅れずに申告してください。
当ホームでは、相続税の申告は親身になって対応してくれる
税理士と提携して行っておりまので、ご安心してお問合せください。
不動産の登記変更の手続
家や土地などの不動産の登記の変更は特に期日の制限はありませんが、
年月が経ったり代替わりした時にトラブルのもとなので、なるべく早く登記の
変更することをお勧めいたします。
なお、不動産の所有権移転の手続きについても良心的な司法書士と提携して
行っておりますので、こちらの手続きも安心してお問合せください。
各種手続きについてはそれぞれの専門家と提携しておりますので上記の手続きにしても、ご安心してお問合せください。

上記手続きを行えば、受取れるものもございますが、あくまで、任意となります。 ご遺族として葬儀後、香典返し・法要・墓地の手配とやるべきことに追われてしまい、本来申請していれば 給付されるはずのものが受け取れなかったり、申請を お忘れになってしまうケースも見受けられます。 是非、当ホームへご連絡の上、安心サポートを ご利用ください。
葬儀後の各種手続き 遺言・相続手続きのサポート